たんぱく質part1~体内での働き~
今回からpart1~4にわけて、三大栄養素のひとつ、たんぱく質について
お伝えします。
お伝えします。
私たち人間の体は約10万種類ものたんぱく質でできています。
骨格や筋肉、皮膚、毛髪、内臓などあらゆる組織を構成する材料です。
骨格や筋肉、皮膚、毛髪、内臓などあらゆる組織を構成する材料です。
たんぱく質はアミノ酸がたくさん結合したものです。
人のたんぱく質を構成するアミノ酸は20種類あり、組み合わせや種類、
量によって、働きの異なるたんぱく質が作られます。
どのたんぱく質も分解と合成を繰り返しながら、一定量を保っています。
体の代謝や機能を調整したりする酵素やホルモン受容体、神経伝達物質
受容体もたんぱく質でできています。
赤血球中の酸素を運搬するヘモグロビンなどの血液の成分、免疫物質も
たんぱく質の一種です。
受容体もたんぱく質でできています。
赤血球中の酸素を運搬するヘモグロビンなどの血液の成分、免疫物質も
たんぱく質の一種です。
また、たんぱく質は1gあたり約4kcalのエネルギーを発生し利用されて
います。
います。
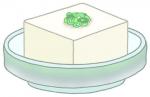

【たんぱく質が不足すると?】
体たんぱく質は分解と合成を繰り返しています。
分解され、アミノ酸になると一部は尿素などになり体の外に出されます。
たえず作り変えられるので、食事から補給する必要があります。
不足すると体力、思考力の低下など体全体の機能低下につながって
しまいます。
また、乳幼児や成長期の子どもの場合は成長障害が起ります。
【とりすぎたら・・・】
特に動物性たんぱく質の食べ過ぎは動物性脂肪やプリン体の量が多く
なることがあります。
それによって動脈硬化や心臓病、痛風などの生活習慣病になりやすい
ので注意が必要です。
なることがあります。
それによって動脈硬化や心臓病、痛風などの生活習慣病になりやすい
ので注意が必要です。
その他、食品から過剰にとった分は尿中に排泄されます。
そのため、腎臓に負担がかかります。
そのため、腎臓に負担がかかります。
糖の代謝を担うインスリンの働きが悪くなることがあります。
カルシウムの尿への排出量が増加して、骨粗鬆症につながる可能性も
あります。

